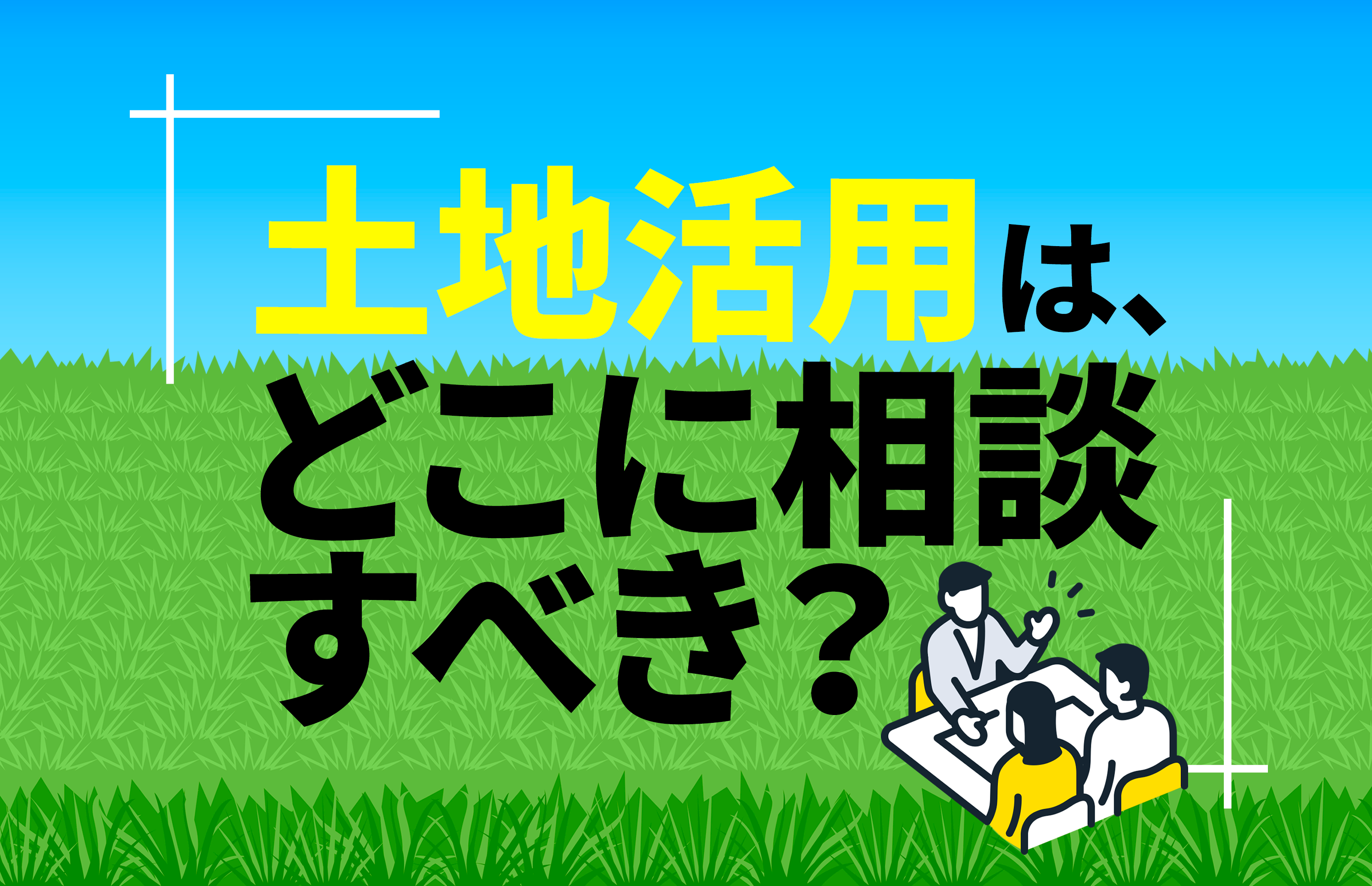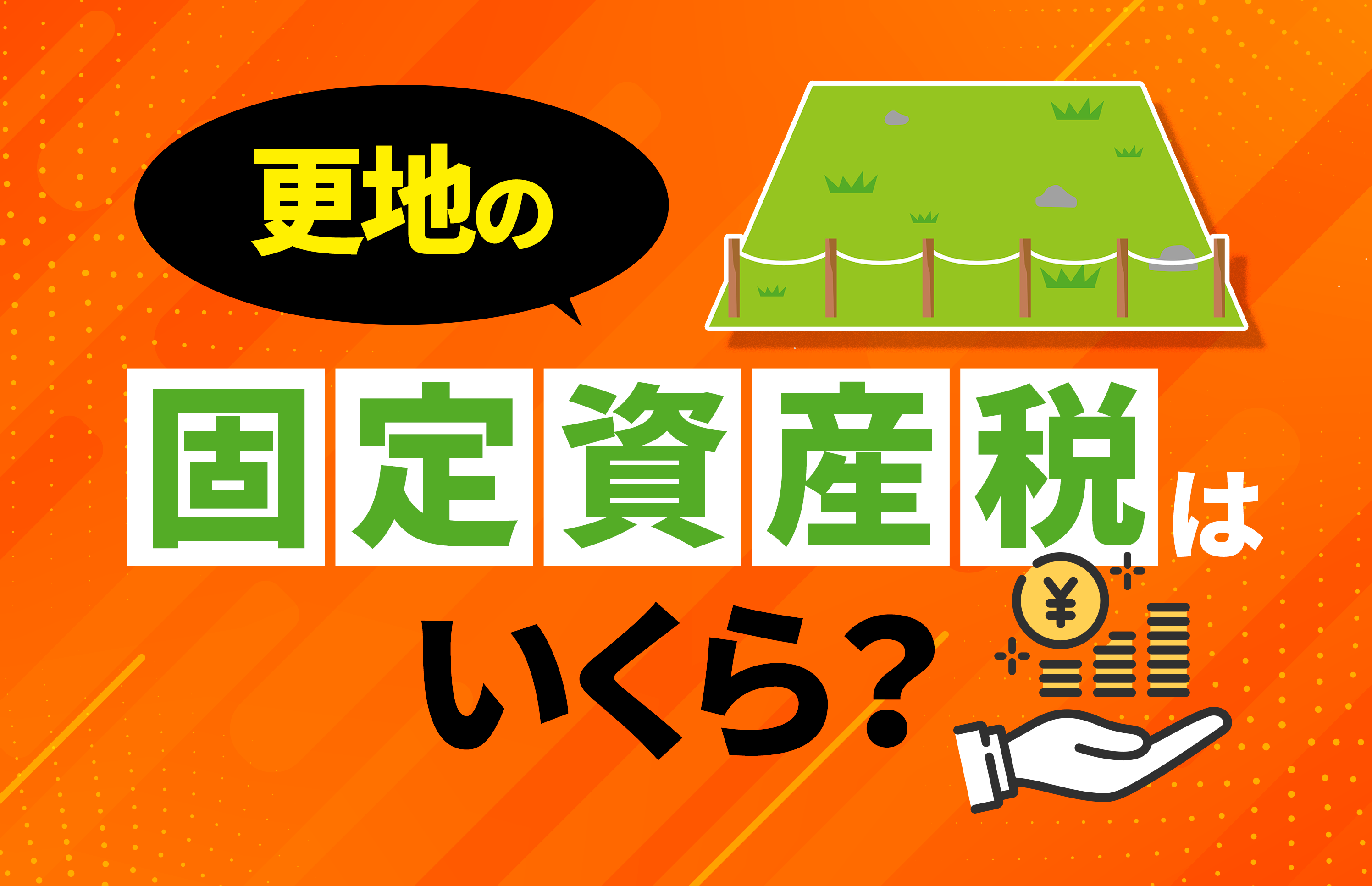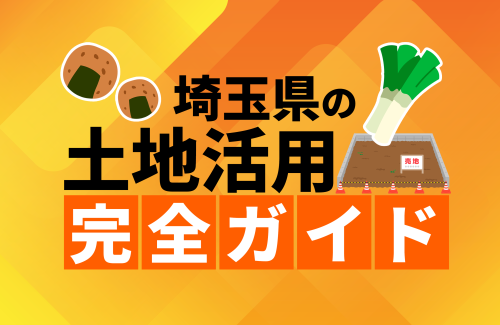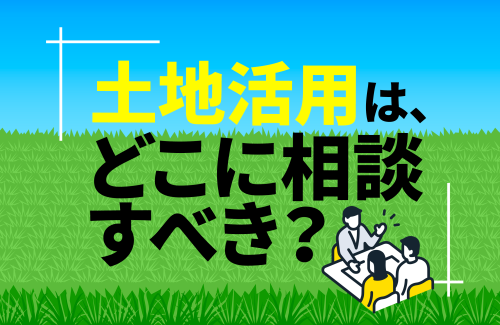⼟地活⽤・賃貸経営コラム
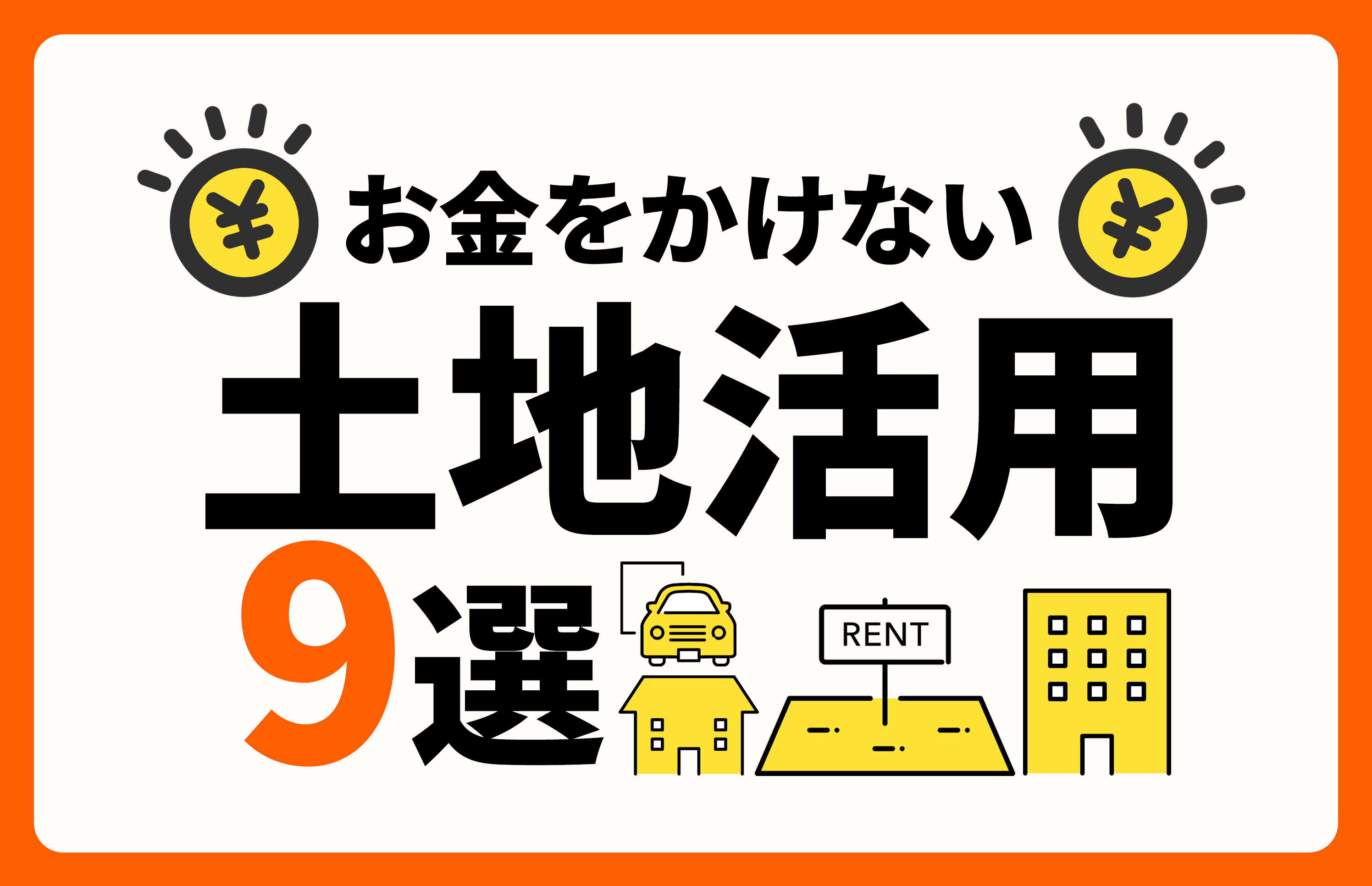
お金をかけない土地活用9選|高収益・高資産価値をつかむ賢い選択肢
お金をかけない土地活用を完全解説。駐車場やトランクルームなど初期費用が低い5つの方法から、自己資金ゼロで高収益を狙える借地事業・等価交換など4つのスキームまで紹介。成功のポイントと注意点も詳しく解説します。
目次
- お金をかけない土地活用とは?
- 土地活用で「お金がかからない」とはどういうことか
- お金をかけない土地活用のメリット
- 【初期費用が低い】手軽に始められる土地活用法5選
- 駐車場経営
- トランクルーム経営
- 資材置き場・建設現場の仮設用地
- 貸し農園・市民農園
- イベントスペース・時間貸し
- 【自己資金ゼロで実現】高収益・高資産価値を狙う土地活用4選
- 借地事業
- 借地事業の仕組みとメリット・デメリット
- 借地事業で実現する土地活用法
- 等価交換
- 等価交換の仕組みとメリット・デメリット
- 等価交換で実現する土地活用法
- 建設協力金方式
- 建設協力金方式の仕組みとメリット・デメリット
- 建設協力金方式で実現する土地活用法
- 土地信託
- 土地信託の仕組みと土地所有者のメリット・デメリット
- 土地信託で実現する土地活用法
- お金のかからない土地活用で成功するためのポイント
- 土地の特性・立地を正確に把握する
- 土地活用の目的を明確にする
- 信頼できるパートナーを選ぶ
- お金のかからない土地活用の注意点とリスク
- 収益性が低くなる可能性がある
- 契約期間と出口戦略を検討する
- 法規制や税制を確認する
- あなたの土地に最適な土地活用を見つけよう
「土地を活用したいけど、まとまった予算がない」そんなお悩みを抱えていませんか?
相続などで受け継いだ土地や、使い道が決まらず遊休地となっている土地は、所有しているだけで固定資産税などの維持費がかかり、家計を圧迫することもあります。ですが、「土地活用には多額の資金が必要なのでは?」と、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。
しかし、土地の条件や活用法によっては、初期費用をほとんどかけずに土地活用を始めることが可能です。
この記事では、お金をかけない土地活用の方法や成功のためのポイント・リスクなどを分かりやすく解説します。
お金をかけない土地活用とは?

そもそも土地活用とは、利用していない土地を有効活用して利益を得る方法です。マンションやアパートを建て賃料を得る活用方法が代表的ですが、それ以外にも活用方法は多岐に渡ります。
さまざまな活用方法があるものの建物を建てる活用が一般的なため「土地活用=お金がかかる」とイメージしている方も多いでしょう。しかし、方法を選べばお金をかけずに土地を活用することが可能です。
土地活用で「お金がかからない」とはどういうことか
ここで「土地活用でお金がかからない」というのは、初期費用が「実質ゼロ」か「極めて少ない」ことを指します。たとえば、マンションを建てて賃料を得る土地活用は、初期費用として建築費用だけでも数千万円以上必要となるため、お金のかかる土地活用です。
一方、ご自身で建物を建てずに土地そのものを貸し出して賃料を得る方法は、自己資金の手出しはないため、お金のかからない土地活用方法です。建物を建てるにしても、外部の事業者が資金を投じて建築する方法もお金をかけずに土地活用ができます。
このように、活用方法を賢く選ぶことで、自己資金を投入することなく、土地から収入を得たり、新たな資産を形成したりすることが可能になります。
ただし、活用方法によって収益性は大きく異なります。一般的にお金をかけない土地活用は、収益性もそれほど高くない点には注意が必要になります。
お金をかけない土地活用のメリット
お金をかけない土地活用のメリットとして、以下のようなことが挙げられます。
- 資金がなくても土地活用をスタートできる
- 初期投資のを抑制し、金銭的なダメージをおさえられる
- 土地の維持管理コストを削減できる
土地は活用せず保有しているだけでも、固定資産税や管理費などのコストがかかります。資金を蓄えてから土地活用しようと数年放置していると、その期間もコストはかかってしまいます。
一方、お金をかけない土地活用であれば、資金がなくても活用をスタートでき、あえて土地を管理する手間や時間はかかりません。また、固定資産税や維持管理分の収入があれば維持管理費の負担の軽減が可能です。
マンションを建てるなど高額な初期投資が必要な土地活用は、ローンを組むにしても自己資金が大きく減少します。さらに、運営中に収支が悪化するとローン破綻するといったリスクもあるでしょう。
その点、初期費用をかけずに土地活用ができれば、自己資金を大きく減らすこともなく、金銭的なダメージをおさえ、安心して活用できます。
【初期費用が低い】手軽に始められる土地活用法5選

ここでは、初期費用がゼロとはいかないまでも、最小限におさえられる手軽な土地活用方法5つを紹介します。
- 駐車場経営
- トランクルーム経営
- 資材置き場・建設現場の仮設用地
- 貸し農園・市民農園
- イベントスペース・時間貸し
駐車場経営
土地を駐車場として提供し、利用料を得る活用方法です。
駐車場には月極とコインパーキングの2種類があります。月極は整地さえすれば青空駐車場として運営できるため、初期費用はほぼかかりません。コインパーキングは機械などが必要になるため、ある程度費用は必要ですが、建物を建てるよりも費用はおさえられます。さらに機械もリースなどを利用すれば初期負担をおさえることができます。
駐車場経営は初期費用をおさえられるだけなく、将来的な土地の転用をしやすいメリットもあります。
手軽に始められる反面、駐車場経営は参入障壁が低く競合が多くなりがちです。また、前面道路の状況や周囲の施設・環境といった立地に需要が左右されやすいので、事前のニーズ調査はしっかりおこなうことが重要です。
トランクルーム経営
土地にコンテナを設置して、利用料を得る方法です。
近年は、季節用品や生活用品・趣味の品などアパートやマンションの収納スペースでは足りない人がトランクルームを利用するケースが増えており、住宅街でも需要が見込めます。また、トランクルームは一度契約すると長期的に利用するケースが多く、安定収入を得やすいのもメリットです。
しかし、トランクルームはあまり収益性は高くありません。用途地域によってはトランクルーム経営できない場合もあるので、事前にご自身の土地の制限は確認しておくようにしましょう。
資材置き場・建設現場の仮設用地
資材置き場や建設現場の仮設用地として土地を貸し出す方法は、初期費用を極めて低くおさえられる土地活用の1つです。建設業者や運送業者などに土地を提供し、その利用料を得ます。
資材置き場や仮設用地であれば更地のまま貸し出すことができ、整地の必要もないため、初期費用を大きくおさえられます。近隣に建設会社が多く存在したり、大規模な開発プロジェクトが予定されていたりするエリアでは、高い需要が期待できるでしょう。
ただし、注意点もあります。資材や重機の搬入・搬出には大型トラックの出入りが必須になり、敷地の形状や前面道路の幅、周辺の交通状況によっては活用が難しい場合があります。
また、頻繁なトラックの往来や、資材の搬入・搬出にともなう騒音などが原因で、近隣住民とのトラブルに発展するリスクも考慮する必要があります。事前に周辺環境への影響を検討し、必要に応じて対策を講じることが重要です。
貸し農園・市民農園
貸し農園・市民農園とは、土地を農地として区分けして耕作希望者に貸し出し、賃料を得る方法です。
建物を建てる・アスファルト舗装する必要がないので初期費用をおさえやすく、交通の便が悪い、土地の形状が悪いといった条件でも収益を得られる可能性があります。貸し農園であれば、自身に農業の知識がなくても活用しやすいのもメリットです。
しかし、貸し農園・市民農園は、利用者がいない時期でも雑草の除去などの手入れの手間が必要です。また、経営方法によっては農業委員会などの承認が必要となるケースもあるので、事前にプロへの相談をおすすめします。
イベントスペース・時間貸し
地域のイベントやフリーマーケット、プロモーション会場などのイベントスペースとして企業などに貸し出して、利用料を得る方法です。
イベントスペースや時間貸しは数時間や1日単位で貸し出せるので、週末だけ貸し出すといった短期間での活用もできます。また、立地によっては利用料を高く設定することも可能です。
ただし、土地にある程度広さが必要になり、交通アクセスがよいなど立地にも需要が左右されることになります。
【自己資金ゼロで実現】高収益・高資産価値を狙う土地活用4選

手軽に始められる活用法に加え、「自己資金を投入せず、いかに大きな収益と高い資産価値を築くか」は、多くの土地オーナー様が抱えるテーマです。ここでは、初期費用を実質ゼロにおさえながら、大規模な資産形成を実現できる4つの賢い土地活用スキームをご紹介します。
- 借地事業
- 等価交換
- 建設協力金方式
- 土地信託
借地事業
借地事業とは、土地オーナー様ご自身が建物を建てるための資金を投じることなく、土地を専門の事業者に貸し出し、その土地に事業者が建物を建設・運営することで、安定した地代収入を得る土地活用方法です。
土地をそのまま貸し出すため、初期費用は実質ゼロで済み、大規模な賃貸マンションやロードサイド店舗、老人ホームといった施設を、オーナー様のリスク負担なしに実現できる点が大きな魅力です。
借地事業の仕組みとメリット・デメリット
借地事業では、土地を借りる人と借地契約を結び、契約期間中は毎月土地の賃料を得ることができます。
【借地契約の種類】 借地契約には、大きく分けて以下の2種類があります。
定期借地契約:あらかじめ定めた契約期間(例:10年、30年、50年など)が終了すると、契約の更新は行われず、土地は更地の状態でオーナー様へ返還されます。
一般借地契約:契約期間が満了しても更新が可能で、オーナー様側が更新を拒絶するには「正当な事由」が必要となります。このため、土地が半永久的に返還されないリスクも考慮する必要があります。
【借地事業のメリット】
初期費用が不要:土地を更地で貸し出すため、オーナー様の自己資金による初期投資は発生しません。
安定した地代収入:長期的な契約により、毎月安定した賃料収入が期待できます。
節税効果:土地の評価額が下がるため、相続税や固定資産税の節税効果が見込めます。
管理の手間が少ない:建物の建設や管理、入居者募集などは全て事業者が行うため、オーナー様の手間がかかりません。
【借地事業のデメリット】
土地の利用制限:契約期間中は、土地オーナー様ご自身で土地を自由に活用することはできません。
長期的な契約:契約期間は種類によって異なりますが、10年や50年といった長期間にわたり土地の利用が制限されます。
土地売却の難しさ:契約期間中の土地売却は可能ですが、借地権付きとなるため、更地と比較して買い手が見つかりにくかったり、価格が下がる傾向にあったりする場合があります。
借地事業で実現する土地活用法
借地事業では借主が建物の建設費用を負担する為、自己資金を投じることなく賃貸マンションやアパート、戸建賃貸、ロードサイド店舗、老人ホームといったさまざまな土地活用が実現できます。
- 賃貸マンション・アパート:土地にマンションやアパートを建築して賃料を得る方法
- 戸建賃貸:土地に一戸建てを建築し賃料を得る方法
- ロードサイド店舗:幹線道路沿いの土地に店舗や飲食店を建設し事業者に貸し出す方法
- 老人ホーム:老人ホームやサ高住などの施設を建設し経営する方法
ただし、借地事業で得られるのはあくまで地代となり、自身で建物を建てて経営する方が収益性は高くなります。
ご自身での経営を検討している方は、ぜひヒノキヤにご相談ください。
ヒノキヤでは、戸建賃貸や賃貸マンションなど土地やお客様の状況に合わせた多彩な土地活用をご提案します。
>>ヒノキヤの土地活用プランはこちらをご覧ください。
等価交換
等価交換とは、土地オーナー様が所有する土地をデベロッパーや建設事業者に提供し、その土地の価値に見合った完成後の建物の一部を取得する土地活用方法です。ご自身で建築費用を負担することなく、新しい賃貸物件や施設を手に入れることができるため、初期費用をかけずに高収益・高資産価値を目指せるスキームです。
等価交換の仕組みとメリット・デメリット
等価交換の仕組みでは、土地の価値と、事業者が負担する建物の建築費用の割合に応じて、完成した建物の一部を土地オーナー様が取得します。例えば、マンションを建築する場合、土地を提供することで、その土地の価値と同等と評価される区分所有権(マンションの数戸分など)を得ることが可能です。
【等価交換のメリット】
初期費用が不要:事業者が建物の建築費を負担するため、土地オーナー様は自己資金を投じることなく、新しい収益物件を取得できます。
事業リスクの低減:建物の企画・建築・販売は事業者が主導するため、土地オーナー様は事業失敗のリスクを軽減できます。
安定した収益源:取得した区分所有権を賃貸に出すことで、安定した家賃収入を得られます。
節税効果:土地が建物付きの不動産に変わることで、相続税評価額が圧縮され、相続税対策としても有効です。
【等価交換のデメリット】
土地の一部所有権を手放す:完成した建物の区分所有権を取得する代わりに、土地の共有持分の一部を手放すことになります。
権利関係の複雑化:複数の権利者が関わるため、権利関係が複雑になりやすく、トラブルを避けるためには信頼できる事業者選びが重要です。
事業期間の長期化:企画から建設、物件取得まで、事業が長期にわたる傾向があります。
等価交換で実現する土地活用法
等価交換を賢く活用することで、土地オーナー様は自己資金を投入することなく、以下のような多様な収益物件のオーナーになり、安定的な収益化や資産形成を目指せます。
賃貸マンション・アパート:都市部の立地であれば、最新設備を備えた賃貸マンションやアパートの区分所有権を取得し、安定した家賃収入を得られます。
戸建賃貸:郊外や住宅地でまとまった土地をお持ちの場合、複数棟の戸建賃貸を取得し、ファミリー層からの長期的な賃貸需要に応えることができます。
老人ホーム・介護施設:高齢化社会において需要が高まる老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、デイサービスなどの施設の一部を取得し、社会貢献と安定収入を両立する活用法も可能です。
商業施設の一部:ロードサイドや駅前などの商業地であれば、商業施設の一部区画を取得し、店舗からの賃料収入を得ることも考えられます。
ヒノキヤは、このような等価交換を通じた土地活用において、豊富な実績とノウハウを持っています。お客様の土地のポテンシャルを最大限に引き出し、ご希望に合わせた最適な収益物件の企画・建設をサポートし、初期費用を抑えながら高収益・高資産価値を実現するためのお手伝いをいたします。
>>ヒノキヤの土地活用プラン
建設協力金方式
建設協力金方式とは、土地オーナー様が建物を建てる際に、入居を希望するテナント(事業者)から建築資金の一部または全部を「建設協力金」として受け取り、その資金で建物を建築する土地活用方法です。完成後はそのテナントに建物を貸し出し、毎月の賃料から建設協力金の返済分を差し引く形でオーナー様の収入となります。コンビニエンスストアやロードサイド店舗、あるいは老人ホームなどでよく利用される、自己資金を大幅におさえながら安定したテナント誘致で収益化を図る手法です。
建設協力金方式の仕組みとメリット・デメリット
建設協力金方式では、まず入居を希望するテナント側が建設協力金という名目で建築費用を土地の所有者に預け入れます。
土地所有者は建築協力金で建物を建築し、建築後はテナント側に貸し出す形です。貸出後はテナント側の賃料から建設協力金の返済額を差し引いた額が土地所有者の収入となります。
【建設協力金方式のメリット】
初期費用を大幅に抑制:テナントからの資金提供により、自己資金の持ち出しや金融機関からの融資額を大幅に減らすことができます。建設協力金は無利子または低金利であるケースが多く、銀行融資よりも有利な条件で資金を調達できる場合もあります。
安定した長期収入:テナントが建設協力金を預けているため、賃料を支払わないと出資金を回収できない構造です。これによりテナントの撤退リスクが低く、長期にわたる安定した賃料収入が期待できます。
事業リスクの軽減:入居テナントが事前に決まっているため、空室リスクを回避でき、事業計画が立てやすい点が大きなメリットです。
【建設協力金方式のデメリット】
テナント依存:万が一、テナントが撤退した場合、その後のテナント誘致が難しい、あるいは建物の用途変更が必要になる可能性があります。
返済期間の長期化:建設協力金の返済期間は長期にわたることが多く、その間は土地利用の自由度が制限されます。
建築費高騰リスク:建築工事着工後に資材高騰などで建築費の追加費用が発生した場合、オーナー様とテナント間で支払いを巡るトラブルに発展する可能性も考慮しておく必要があります。
建設協力金方式で実現する土地活用法
建設協力金方式を上手に活用することで、土地オーナー様はテナントからの資金提供という好条件を活かし、自己資金の持ち出しをおさえながら、以下のような特定のテナントが入居する大規模な施設建設を実現できます。
ロードサイド店舗:幹線道路沿いの土地にコンビニエンスストアやドラッグストアなどを建設。テナントの事業計画が明確で、長期契約による安定した賃料収入が期待できます。
老人ホーム・介護施設:高齢化社会で需要の高い老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などを建設。運営事業者からの建設協力金で施設を建て、長期入居契約を通じて安定収益を得られます。
医療クリニック・調剤薬局:地域住民に必要な医療クリニックや調剤薬局を誘致。専門性の高いテナントが長期入居することで、安定した賃料収入が見込めます。
土地信託
土地信託とは、土地オーナー様がご自身の土地を信託銀行や信託会社に預け、その土地の運用・管理を全て任せることで、運用益に応じた配当金を得る土地活用方法です。建物の建築計画の立案から建設、その後の賃貸管理や運営まで、土地活用に関する費用や手間は一切かからず、プロの専門知識とノウハウで収益化を目指せる点が最大の特徴です。
土地信託の仕組みと土地所有者のメリット・デメリット
土地信託では、土地オーナー様が所有する土地を信託銀行や信託会社に「信託」し、一定期間その運用を委託します。信託された土地は、信託会社が市場調査に基づき最適な活用計画を立案し、建物の建築費なども信託会社が負担して事業を進めます。運用で得られた利益の一部は、配当金として土地オーナー様の収入となります。
【土地信託のメリット】
初期費用が不要:建物の建築費や運用コストは信託会社が負担するため、土地オーナー様は自己資金を投じる必要がありません。
手間がかからない:企画・建築・管理・運営の全てをプロに任せられるため、土地活用の専門知識や経験がなくても、手間なく収益化を目指せます。
リスクの軽減:専門家による市場調査と運用計画に基づき事業が進められるため、個人の判断による失敗リスクを低減できます。
【土地信託のデメリット】
配当金は運用成果に応じる:配当金は運用益によって変動するため、必ずしも一定の収益が保証されるわけではありません。損失を被るリスクもあります。
信託できる土地の条件:信託会社が利益を見込める土地であることが前提となるため、立地や形状によっては信託契約が難しいケースもあります。
信託報酬が発生:信託会社に支払う手数料(信託報酬)が発生します。
土地信託で実現する土地活用法
土地信託を活用することで、土地オーナー様は土地活用の専門知識やノウハウがなくても、プロの信託会社が主体となり、土地のポテンシャルを引き出す活用法を実現できます。
賃貸アパート・マンション:信託会社が市場ニーズを分析し、最適な規模やデザインの賃貸アパートやマンションを建設・運営します。オーナー様は、その賃料収入から得られる配当金を受け取ることができます。
老人ホーム・介護施設:高齢化社会に対応した老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの建設・運営も、信託会社の専門的な知見により実現可能です。安定した需要が見込まれるため、長期的な配当が期待できます。
商業施設・オフィスビル:立地によっては、商業施設やオフィスビルを建設し、テナントからの賃料収入を配当金として受け取ることも可能です。
このように、土地信託は、土地オーナー様が自己資金や手間をかけることなく、大規模な土地活用を通じて安定的な収益を目指せる有効な手段です。
お金のかからない土地活用で成功するためのポイント

お金がかからないとはいえ、土地活用で成功するにはいくつかポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、土地活用のリスクを最小限におさえ、安定した収益を確保するために押さえておきたいポイントとして、以下の3つを解説します。
- 土地の特性・立地を正確に把握する
- 土地活用の目的を明確にする
- 信頼できるパートナーを選ぶ
土地の特性・立地を正確に把握する
土地活用方法にはさまざまな種類があり、何が最適かは土地の特性や立地などによって異なります。
土地の形状や面積・接道状況など土地自体の特性だけでなく、周辺環境などのニーズや交通アクセスといった強みをまずは正確に把握するようにしましょう。不動産会社などに相談する場合でも、正確な情報を最初に提供できるようにすれば効率よく相談を進めやすくなります。
また、土地には用途制限などの法的な制限がかかっているケースもあります。活用方法を決めてから制限がわかると計画から建て直しになる恐れもあるので、事前に用途地域や制限なども確認しておきましょう。
土地活用の目的を明確にする
土地活用を行う目的は、土地オーナー様一人ひとり異なります。主な目的としては、以下のような点が挙げられるでしょう。
- 収益の最大化:高い賃料収入や売却益を目指す。
- 相続税対策:相続税の負担を軽減する。
- 土地維持費の軽減:固定資産税などのランニングコストを賄う、または減らす。
- 地域貢献:地域社会に役立つ施設を建設する。
例えば、「できるだけ大きな収入を得たい」のか、「まずは固定資産税分を賄えれば十分」なのかによって、選ぶべき土地活用方法は大きく変わってきます。維持管理費の負担を軽減したいだけなのに、多額の費用をかけて土地活用をすれば失敗するリスクも大きくなる可能性があります。
最適な土地活用方法を選ぶためにも、事前に土地活用の目的を明確にしておくことが大切です。また、目的を明確にする際には、「いつまでに・いくら」など、より具体的な目標を立てると土地活用方法も選びやすくなります。
信頼できるパートナーを選ぶ
土地活用は、活用方法の選定から設計、運用、そして法規制や税務に至るまで、多岐にわたる専門知識を要します。そのため、信頼できるパートナーの存在は、成功を左右する不可欠な要素となります。
特に、借地事業や等価交換、建設協力金方式といった初期費用をおさえつつ資産形成を目指す方法を選ぶ場合は、事業者の信頼性や企画力、長年にわたるサポート体制が重要です。豊富な実績だけでなく、お客様の土地の特性や目的に合わせた柔軟かつ具体的な提案ができるかをチェックすることが大切です。
業者を選ぶ際には、実際に提案されるプランの内容だけでなく、これまでの実績や顧客からの評判、専門家の資格保有状況など、複数社を比較検討するようにしましょう。ヒノキヤのような、多様な土地活用スキームに精通し、建設から運用まで一貫してサポートできる企業を選ぶことが、安心して土地活用を進めるための鍵となります。
お金のかからない土地活用の注意点とリスク

お金のかからない土地活用は、初期費用をおさえられますが、リスクがないわけではありません。どんな土地活用であっても潜在的なリスクや注意すべき点があるため、それらを理解したうえで土地活用を進めることが大切です。
ここでは、お金のかからない土地活用の注意点やリスクとして、以下の3つを解説します。
- 収益性が低くなる可能性がある
- 契約期間と出口戦略を検討する
- 法規制や税制を確認する
収益性が低くなる可能性がある
お金のかからない土地活用法は、基本的にご自身でマンションやアパートを建設・運営するといった方法に比べると、得られる収益が相対的に控えめになる傾向があります。
ローン返済などの金銭的リスクを抑えやすいという大きなメリットがある反面、初期投資が少ない分、手元に残る収入が大規模な開発ほど大きくないと感じる可能性もあります。とくに、駐車場や貸農園は利用単価が低く、収入が限定的になるおそれがあります。また、借地事業や等価交換の場合も、地代収入や家賃収入のシミュレーションを慎重に行い、期待するリターンが得られるか冷静に判断することが重要です。
事前に、長期的な収入が見込めるか、希望する収入を実現できるかは、慎重に検討することが大切です。
契約期間と出口戦略を検討する
借地事業や等価交換、建設協力金方式、土地信託といった方法は、いずれも数十年単位の長期的な契約となるのが一般的です。契約期間中は土地は自分で好きに活用できなくなるため、将来活用や売却などの可能性がないかは事前に考慮するようにしましょう。
また、どんなに長期の契約であっても、期間はいつか終了するものです。契約期間終了後に、土地を更地に戻して別の活用をするのか、それとも再契約や売却を検討するのかなど、「出口戦略」まで見据えた計画を立てておくことが極めて重要です。これにより、将来的な選択肢を広げ、不測の事態にも対応できるようになります。
法規制や税制を確認する
土地を活用する際には、建築基準法や都市計画法、消防法といった基本的な法律に加え、地域ごとの条例など、さまざまな法規制をクリアする必要があります。
例えば、土地に建てられる建物の種類やサイズなどは用途地域や建ぺい率・容積率などにも左右されます。また、土地活用の方法によっては、申請が必要になったりかかる税金の種類や金額が変わったりもします。特に、相続税対策としての土地活用では、税務上の優遇措置を最大限に活用するための専門的な知識が必要です。
これらを専門家に相談しながら計画を進めることで、法的なトラブルを未然に防ぎ、希望の土地活用を実現できるだけでなく、最適な税務対策によって節税効果を最大化することも可能になります。
あなたの土地に最適な土地活用を見つけよう
ここまで、お金のかからない土地活用方法の種類や成功のポイント、注意点やリスクなどをお伝えしました。
土地活用は方法を選べば、自己資金ゼロや最小限におさえて収益化を目指すことが可能です。資金がないからと土地活用を躊躇せずに資金ゼロで土地活用をスタートすることで、維持管理の負担を軽減できるなどのメリットがあります。
しかし、お金がかからない土地活用でもリスクや注意点はあります。また、最適な土地活用は土地の状態や目的によって異なるものです。まずは、土地の状態や活用目的などを整理し、専門家に相談しながらご自身の土地に最適な活用方法を見つけることをおすすめします。


 RANKING
RANKING